※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
こんにちは!つなです。
7年で資産1000万円に到達し、現在はゆるく働くサイドFIREを目標に活動しています!

産休育休中、思ったより生活費が足りないかも…?
どうやって家計管理したらいいんだろう?
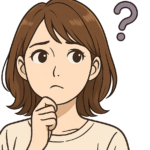
貰えるお金も多いみたいだけど、どうやって申請したらいいんだろう…
この記事では、こんなお悩みを解決します!
公的支援制度やサポートとおと&つな家が出産前に見直した家計管理についてお話しします。
最後まで読むと、「産休・育休中の生活費が足りないかも…」という不安が、「我が家はこうすればいいかも!」に変わるはずです。
産休・育休中に生活費が足りなくなる理由
育児に必要なアイテムの支出が増える
出産前にもチャイルドシート、ベビーカーなど、ベビーグッズの準備や引っ越しでお金がかかりました。
さらに赤ちゃんを迎えると、思っていた以上に出費が増えます。
オムツ、ミルク、哺乳瓶など、小さな消耗品でも毎月積もると想定外の金額に。
出産後は定期的な支出が月6〜8万円増える想定です。
想定金額月6〜8万円を試算した方法は、こちらの記事で紹介しています。
各ご家庭の子育て方針によって増える支出額は変わりますので、合わせてご覧ください♪
一時的に収入が減る
産休・育休中は出産手当金や育児休業給付金などもらえるお金がさまざまあります。
一方で、会社の給与額と比べると減ることが多く、支給までに2〜3ヶ月の時差があることも。
さらに、住民税など支払いが必要なお金もあります。

友人から「産休前にもっと現金を貯金しておけばよかった…」と聞いて、現金貯金比率を上げました。
毎月の支出が把握できていない
出産前は「夫婦別財布」で生活に必要な支出を折半していました。
個人で使える自由なお金があって良い一方で、個人で支払っている「見えない支出」もありました。
結果、生活全体のコスト感が見えにくいことが課題でした。

妊娠・出産をきっかけに「このままで大丈夫?」と話し合うきっかけができて良かったです。
産休・育休中にもらえるお金
出産・育休で収入が減る中、「お金の不安」を少しでも和らげるには、公的制度を知っておくことが大切です。
ここでは出産前に調べて助かった、もらえるお金・免除されるお金・支払いが必要なお金をまとめました。
出産手当金(産前・産後休業給付金)
健康保険(協会けんぽ・健保組合)加入している会社員・パートが対象です。
給与が支払われない産休期間に「出産手当金」を受け取ることができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 産前42日+産後56日(多胎妊娠は産前98日) |
| 支給額の目安 | 標準報酬日額の約2/3(1日あたり)×休業日数分(非課税) |
出典元:全国健康保険協会公式サイト「出産で会社を休んだとき」
出生後休業支援給付金・育児休業給付金
雇用保険に加入している会社員・パートが対象です。
育休中に「出生後休業支援給付金(2025年4月創設)」「育児休業給付金」を受け取ることができます。
| 育休期間 | 給付率 |
|---|---|
| 初日(産後57日)~28日 | 月給の80%(所得税・住民税が非課税) |
| 29~180日 | 月給の67%(所得税・住民税が非課税) |
| 181日以降 | 月給の50%(所得税・住民税が非課税) |
出産手当金と育児休業給付金の違い
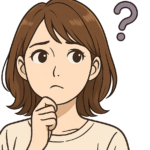
出産手当金と出生後休業支援給付金・育児休業給付金と同じでしょ?
実は、出産手当金と出生後休業支援給付金・育児休業給付金は、給付される運営機関が異なるんです。
この機会に違いを知っておくと良いかもしれません!
| 項目 | 出産手当金 | 出生後休業支援給付金 育児休業給付金 |
|---|---|---|
| 給付元 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 対象期間 | 産休中(産前42日+産後56日) | 育休中(産後57日〜最長2年) |
| 支給額 | 月給の約2/3(日額計算) | 月給の67%→50% (期間により変動) |
| 所得税・住民税 | 非課税 | 非課税 |
| 備考 | 会社から給与が出ている場合は対象外 | 就労状況によって停止・再開あり |
その他の支援制度(児童手当・出産育児一時金・横浜市の支援制度)
出産前後の支援制度はまだまだあります!
神奈川県横浜市独自の制度も含めてご紹介します。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 妊婦健診の助成券 | 自治体が発行する助成券(横浜市は8.2万円分) |
| 出産育児一時金 | 健康保険から50万円支給 |
| 児童手当 | 3歳未満:月1.5万円 3歳以上高校生年代まで:月1万円 |
| 妊婦健康診査費用助成金 | 横浜市から5万円の助成金 |
| 出産応援金・妊婦のための支援給付 | 横浜市から5万円の給付金 |
| 出産費用助成金 | 横浜市から最大+9万円の助成金 |
出典元(出産育児一時金):全国健康保険協会公式サイト「子どもが生まれたとき」
出典元:こども家庭庁公式サイト「児童手当制度のご案内」
出典元:横浜市公式サイト「妊婦健康診査費用助成金」
出典元:横浜市公式サイト「出産応援金・妊婦のための支援給付」
出典元:横浜市公式サイト「出産費用助成金」
産休・育休中に支払いが免除されるお金
社会保険料
産休・育休中は社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が全額免除されます。
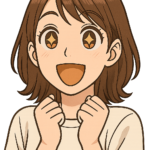
将来貰える年金が減るんじゃないの…?と思っていた私にとって、
支払いが免除されても将来貰える年金額に影響しないのは驚きでした!
夫の扶養に入った場合、厚生年金保険料を「払ったもの」としてカウントされず、
将来もらえる年金額が少なくなる可能性があります
出典元:日本年金機構公式サイト「保険料の免除等(産休・育休関係)」
所得税・各種控除
育休中は会社から給料が出ない分、課税所得(税金の計算に使われるお金)が少なくなります。
そのため、所得税やこの後解説する住民税が軽減される可能性があります。
また、控除制度(税金が安くなる仕組み)を使って、家計の負担を減らせるチャンスがあります。
産休・育休中に支払いが発生するお金
産休・育休中は、貰えるお金や免除されるお金が多くありがたいですよね。
一方で、支払いが発生するお金もありますので要注意!

収入がない時期に、20万円近い請求が来た友人の話は衝撃的でした。
住民税
住民税は「前年の所得」に基づいて翌年に課税されるしくみです。
育休前年はフルタイム勤務のため、育休中に住民税の支払いが必要です。
| 年度 | 勤務状況 | 住民税 | 年収(例) | 住民税(例) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | フルタイム勤務 | 2023年課税分を支払う | 400万円 | 約20万円 |
| 2025年度 | 育休(収入ゼロ) | 2024年課税分を支払う | 0万円 | 約20万円 |
| 2026年度 | フルタイム勤務 | 2025年課税分を支払う | 400万円 | ほぼゼロ |
住民税は課税と支払いのタイミングに“1年のズレ”があります
育休に入った翌年は負担が減るとはいえ、収入が少ない時期に貯金で備えるのは難しいですよね…。
産休・育休前に先取り貯金の仕組みをつくることで、あっさり解決できるかもしれません。
私つなの経験談をまとめていますので、よろしければこちらの記事も合わせてご覧ください♪
おと&つな家の生活費対策3選
生活費の負担割合を再設計
我が家はこれまでフルタイムで共働きだったため、半額ずつ(10万円ずつ)出し合っていました。
出産後は、私の収入が減ることを見据えて“収入の7割を共有口座に入金”する方法に変更しました。

今まで通り折半だと、個人で使えるお金がなくなるし、不公平に感じる…
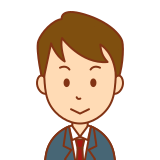
単純に負担金額が増えるのはプレッシャーに感じるなぁ…
いい方法はないかな?

どっちも「収入の7割を出し合う」なら平等だね!
結果、夫おとの生活費負担が増え、妻つなの個人で使えるお金が減ったことに変わりありません。
それでも「収入に対する割合で出し合う」という公平性を保つことでお互いに納得できました。
支出を“見える化”して共有
生活費をどう出すかだけでなく、何にいくら使っているかを“見える化”することも大事です。
現在は、夫婦2人暮らしの生活費+6〜8万円と予想しています。
でも、実際に子どもと一緒に暮らしてみないと、本当の生活費はわかりません。
なるべく育児に時間を使いたいので、支出を簡単に見える化できるような仕組みを作りました。
3年間この方法で継続できているので、出産してからも調整しながらやりくりができると思います。
支出を見える化する仕組みづくりの詳しい方法は、こちらの記事で紹介しています。
忙しい共働き夫婦は家計管理に時間をかけないのが一番!あわせてご覧ください♪
ふるさと納税で節約
ふるさと納税は、先ほどご紹介した住民税の軽減に貢献するだけではありません。
生活費の節約にも貢献してくれる、とっても頼りになる「ふるさと納税」。
生活費を“削る”よりも、“満足度が変わらない方法へ置き換える”とストレスが少なくなります。
日用品や食品を実質2,000円で手に入れられるのが大きな魅力です。
しかも、日用品は全てふるさと納税でまかなうことができ、年間2万円ほど生活費が浮きました。
実際に我が家がもらっている返礼品はこちら👇
育休中は収入が減るので「寄付上限金額」に要注意!
ふるさと納税の具体的なやり方は、こちらの記事で紹介しています。
実は、節約だけでなく地方特産品を美味しくいただいたり、ご褒美品としても活用しています!
生活満足度を変えずに生活費を節約する、お得な方法を一緒に活用しましょう♪
出産後の夫婦別財布を継続する理由
出産後は家計一本化?別財布?
出産後は、収入を全てまとめて「家計一本化」するご家庭が多いのではないでしょうか?
私も家計一本化が良いと漠然と思っていましたが、話し合いの結果、別財布を継続することに。
私が納得した考え方は「お互いの自由を最大限に尊重して、経済的に自立した状態を保つ」です。

おこづかい制度など制限をつけてしまうと、自由がなくなってしまう気がする
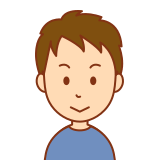
どちらかの収入だけに頼る生活は、何かあった時心配…
そんな私たちの価値観を尊重してくれるのが、夫婦別財布の継続だと納得しました。
夫婦別財布を継続するためにやったこと
納得できる公平な折衷案を作る
家族の家計管理はチーム戦。チーム全員が納得いく方法を模索しました。
我が家は、「収入の7割」を出し合うことで納得しました。
残りの3割は好きに使って良い(お互い口出ししない)ことで、自由に使えるお金も残ります。
金額ベースで見ると夫おとの方が負担額が大きくなりますが、割合で表すことで納得度UP。
工夫しながら各家庭(チーム)に合った方法を模索できると良いですね♪

私の方が自由に使えるお金は減りますが、稼ぐモチベーションになりました!
定期的に話し合う場を作る
我が家は月1回10分、家計ミーティングを習慣にしています。
家計簿アプリ「マネーフォワードME」を見ながら、振り返りを行います。
ガチガチな会議ではなく、のんびりしている時間に「ちょっと話そっか~」くらいのテンションで実施しています。
まとめ|知識と工夫で“生活費足りない問題”は解決できる
今回は、産休・育休中に「生活費が足りない問題」を解決するために、公的支援制度やサポート・おと&つな家が出産前に見直した家計管理についてお話ししました。
出産後のお金に関する漠然とした不安を解決するには、制度やサポートの内容を理解することが重要です。
さらに、家族の家計管理は「チーム戦」。
夫婦で話し合いができる環境を出産前から作っておくことの大切と感じた実体験もお話ししました。
出産前から始める小さな対策の積み重ねが、「もう無理かも…」を「これならやれるかも!」に変えてくれます。
まずは「できることから」でOK。あなたらしいやり方を見つけてくださいね♪
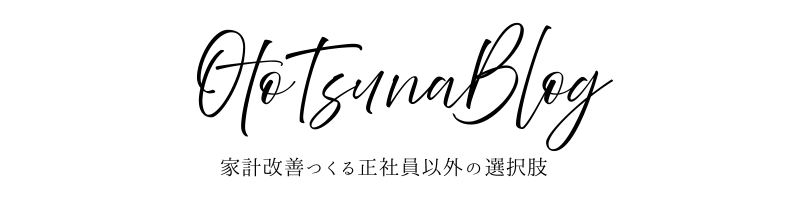









コメント